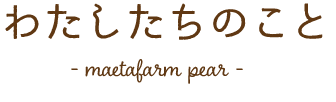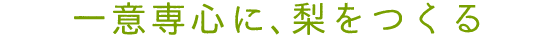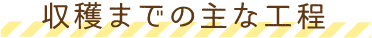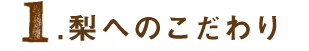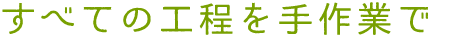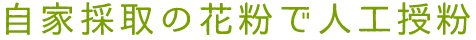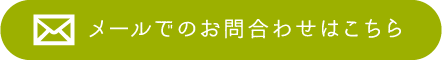まえた農園は、4代目園主・前田真也と母の二人で営んでいます。
2012年、父の急病・他界を期に長男である私が後を継ぎました。
それまではサラリーマンをしていたのですが、長年にわたって家族が大切に育んできた梨の木と、
毎年まえた農園の梨を楽しみにしてくださっているお客さまの顔を思い浮かべたとき、
進むべき道は決まっていました。
代々受け継がれてきた栽培のノウハウを知る母と、
父の代から農園のことを気にかけてくださっている多くの方々の支えられ、
それまでと変わらぬ梨づくりに取り組むことができています。
地元大学や園芸試験場で行われる研修会等に積極的に参加して、知識や技術を高める努力も怠りません。
最近では果樹栽培、農園経営の面白さを実感できるまでに。新品種の育成、新しい栽培技術にも挑戦中です。
まえた農園の梨を手に取ったとき、口にほおばったとき、お客さまが心から感動するような梨をつくりたい。
そんな思いを込めて、毎日一生懸命梨を育てています。
この農園に梨の木を植えたのは、私の曾祖父だそうです。
それから約100年、前田家はこの地で果樹園を営んできました。
鳥取県に初めて二十世紀梨の苗木が植えられたのが1904(明治37)年ですから、
当園はその歴史と肩を並べて時を刻んできたといえます。
最初はなかなかうまくいかなかったようですが、祖父の代には軌道に乗り、
大玉で高品質な梨栽培に力を注いだといいます。
父は市場に出荷するスタイルをやめ、お客さまと直接顔を合わせて販売する直売方式に切りかえました。
また、観光農園として梨狩り体験も行っていました。
この頃父が作業場兼選果場として建てたログハウスは、今ではこの農園のシンボル的な存在となっています。
農園にはリンゴやブルーベリー、梅、栗なども少し植えられており、夏から秋にかけて
様々な果実の収穫に恵まれます。







梨は水分の多い果物です。口にほおばったときのシャッキリとした食感、かむほどに爽やかな甘さの果汁があふれ出すみずみずしさが最大の特徴。もぎ取ってからお客さまの口に運ばれるまでの時間が短ければ短いほど、その美味しさを存分に味わっていただくことができるのです。
遠く離れたお客さまにも「できるだけ新鮮な梨を味わってもらいたい」という思いから、まえた農園では、食べ頃を向かえた梨を朝もぎ取り、すぐに選果・箱詰めして、その日のうちに発送しています。

梨はとてもデリケートな果物。収穫までには、剪定、摘蕾・摘花、人工授粉、袋かけなどたくさんの手間がかかりますが、我が子のように大切に育てれば品質の良い梨ができます。ですから当園では、ほとんどすべての工程を手作業で行っています。 12月~3月に行う「剪定」は、次の年の出来映えに影響する重要な作業。枝全体に均等に養分がいきわたるよう、バランスを考えながら切り落としていきます。
「袋かけ」の作業は、果実を病害虫から守るために欠かせません。二十世紀梨は、実が小さいうちは小袋、大きくなってきたら大袋と、袋かけを2回行わなければいけないので特に大変です。しかし、そのおかげで美しい緑色の二十世紀梨が出来上がるのです。

当園では、定められた基準値以下の減農薬栽培を心がけています。また、使用する肥料は、ぼかし肥料や油かすといった有機肥料が主体です。
雑草の生長を抑えるためには、干し草で地面を覆い隠す「草マルチ」という方法を用いています。この方法は土の乾燥防止にも最適。まえた農園のある西郷地区周辺はもともと水が少ない地域で、夏場は水不足に陥りやすいのですが、草マルチを施すことで地面の保水力が増し、梨の玉太りが良くなるのです。自然素材である干し草は、枯れればそのまま有機肥料となるので“一石三鳥”です。

二十世紀梨をはじめ多くの梨は「自家不和合性」の性質を持っており、同品種の花粉を受粉しても実はなりません。ですから、あらかじめ他品種の花粉を用意して、梨の花が咲く4月上旬に人工授粉を行います。
ほとんどの梨農家が人工授粉用の花粉を購入するのですが、まえた農園では昔から花粉を自家採取しています。農園にある「長十郎」などの赤梨が開花し始めたら、花を摘んで花粉を取り出すのです。そして二十世紀梨の花が咲いたら、晴天の日を狙って一気に授粉作業を行います。